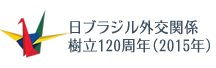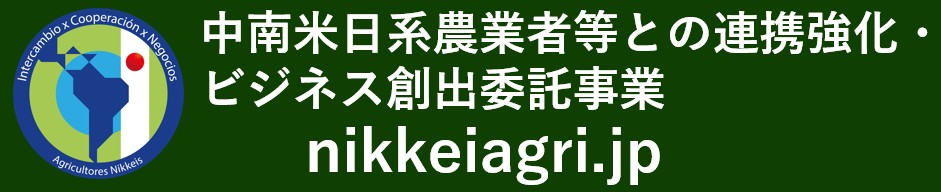2008年 日伯交流年・ブラジル移住100周年
ブラジルへの最初の移民船「笠戸丸」が神戸港を出港した1908年4月28日からちょうど100年を経た2008年4月28日、兵庫県公館において皇太子殿下ご臨席のもと記念式典が開催されました。
ブラジル移住100周年を祝うために、外務省が主導で日伯交流年実行委員会が組織されたと同時に、兵庫県では日伯協会が中心となり官民挙げて日伯交流年兵庫県実行委員会が立ち上げられました。委員長には当協会の理事長西村正が就任し、2008年は一年間にわたり、日伯交流年兵庫県実行委員会や日伯協会が主催して多くの事業・行事が実施されました。
このページでは、日伯交流年兵庫県実行委員会と日伯協会の主な事業と行事の写真や挨拶がご覧いただけます。
 |
 |
2008年4月28日 - 日伯交流年・ブラジル移住100周年記念式典
皇太子殿下のおことば
 日伯交流年・ブラジル移住100周年記念式典を、日本ブラジル交流年の名誉総裁として、皆さんと共にお祝いできることを大変うれしく思います。
日伯交流年・ブラジル移住100周年記念式典を、日本ブラジル交流年の名誉総裁として、皆さんと共にお祝いできることを大変うれしく思います。
先週24日には、天皇皇后両陛下のご臨席の下、東京で、日本ブラジル交流年・日本人ブラジル移住100周年記念式典及びレセプションが、ブラジル政府代表、ブラジルの各界で活躍している日系人の代表を始め、多数の両国関係者の出席を得て開催されました。
さらに、本年6月には、ブラジル各地での記念式典や行事に出席するため、私のブラジル訪問が両国政府で検討されています。
本日からちょうど100年前、明治41年4月28日午後5時55分、最初のブラジル移民船である笠戸丸(かさとまる)がこの神戸の地を出航しました。今日のように航空機やインターネット、衛星放送などの通信手段が発達していなかった当時、現地での自然環境や病気、言語や文化についての情報は乏しく、移住者の不安、苦労はいかばかりであったかと思います。
私が最初にブラジルという国を身近に感じたのは、昭和42年に行われた日本とブラジルのサッカーの試合を観戦したときであったと思います。当時7歳であった私は、その試合を通し、ブラジルはサッカーがとても強い国であるという印象を持ちました。
笠戸丸(かさとまる)から70年余の昭和57年、私はブラジルを訪問しました。笠戸丸(かさとまる)が52日をかけた距離を航空機で2日で移動し、ブラジルの皆さんに歓迎していただきました。ブラジルの国土の広さ、多様性、人々の明るさが印象に残っています。そして何よりも、血を分けた同胞である日系人の皆さんのこれまでの地道な努力に対するブラジル社会の高い評価が両国関係の礎となっていることを強く感じました。
笠戸丸(かさとまる)から100年後の今日、日本とブラジルの関係は、100年前には想像もできなかったほど緊密になり、数多くの日系人がブラジルから日本に来て生活するようにもなりました。先週、東宮御所でブラジルで活躍されている若手日系リーダー25名にお会いし、また、24日の式典で、日本の小学校で共に勉強している日本人と日系人の児童10名による日本とブラジルの懸け橋になりたいという発表を聞き、これからの両国関係の発展に大いなる希望を感じ、感銘を受けました。
国際社会の中で日本とブラジルは、諸課題の解決に向けて一層緊密な連携が求められています。日系人の皆さんの長年にわたる努力への敬意と日本人移住者を温かく受け入れてきたブラジル政府、国民への感謝を忘れずに、両国関係を将来にわたって発展させていきたいと思います。私自身も、ブラジル訪問を通じて、両国関係の更なる発展に貢献したいと考えています。本日の式典に参加された皆さんが、更なる両国の友好交流の懸け橋として活躍されることを心から願い、式典に寄せる言葉といたします。
日伯交流年兵庫県実行委員会・委員長 西村正の挨拶
 皇太子殿下、ご列席の皆様、
本日、「日伯交流年・ブラジル移住100周年記念式典」をこのように盛大に開催できますことを、日伯交流年兵庫県実行委員会委員長として、大変嬉しく思います。
皇太子殿下、ご列席の皆様、
本日、「日伯交流年・ブラジル移住100周年記念式典」をこのように盛大に開催できますことを、日伯交流年兵庫県実行委員会委員長として、大変嬉しく思います。
1908年(明治41年)4月28日午後5時55分、歴史に残る第1回ブラジル移住船「笠戸丸」が神戸港を出航し、ブラジル移住の歴史が幕を開けてから、今日でちょうど100年になります。現在、神戸港の一隅、広い海を一望できるメリケンパークには、「希望の船出」と名づけられた親子の像が立っています。希望と一抹の不安が入り混じったまなざしで水平線の彼方を見つめる、若き移住家族の像です。神戸は、まさに25万人におよぶ移住者にとって、日本での最後の日々を過ごした思い出の地でありました。
日本からブラジルに渡った移住者とその子孫の皆さんは、ブラジル社会の発展に大きく貢献するとともに、日本人の勤勉さを広く伝え、日本の名声を高めてこられました。今やブラジルの日系人社会は150万人規模へと拡大し、日系6世が誕生するまでになっています。祖国を離れ、不屈の精神のもと困難を乗り越え、このような立派な日系社会を築いてこられた皆さんのご努力に、改めて深い敬意を表する次第です。
さて、グローバル化時代を迎え、世界的な人の往来がこれまでになく活発になる中、国際間の協力関係をいかに築くかということが喫緊の課題となっています。このような中、幸いなことに日本とブラジルには100年にわたって先人達が築いてきた友好の礎があります。
日伯交流年で行われる交流事業を通じ、この友好関係が一層揺るぎないものとなることを心から願うとともに、次の100年に向けて、若い世代を含めた多くの方々に両国間の交流に対する関心を高めていただき、友好交流の新たな歴史を刻んでゆけることを願っております。
ブラジル連邦共和国 在名古屋総領事
ジェラルド・アフォンソ・ムジ氏
 本日4月28日は、まさに781名の日本人がサントス港に向けて神戸港を出発した時より100年目にあたる歴史的な日であります。
本日4月28日は、まさに781名の日本人がサントス港に向けて神戸港を出発した時より100年目にあたる歴史的な日であります。
日系移民の足跡は人口の流出と回帰の歴史であります。それは、様々な世代の家族が再会する場でもあります。今日ブラジルには約150万人の日本人の子、孫、曾孫にあたる二世、三世、四世、そして六世の日系人が暮らしておられます。
一方20年前、両国間の人の流れは逆転し、現在日本には32万人余りのブラジルからの移民が居住しています。日本とブラジルの関係は、政治、経済、貿易と文化の枠を超えて存在するのです。それは家族的なものであり、百年をかけた源流への回帰でもあります。
最後に、このような盛大な会が開催されました事を心よりお祝い申し上げ、私の挨拶に代えさせていただきます。
ブラジル日本移民百周年記念協会 会長 上原幸啓氏
 80歳という年齢に達しました今日、私は人生において最も栄誉ある瞬間を迎えております。
80歳という年齢に達しました今日、私は人生において最も栄誉ある瞬間を迎えております。
この記念式典は、人々の人生を変え、また他国民との絆を強め、さらに最大の海外日系社会を形成した一つの歴史の始まりを象徴的に表しております。
本式典に出席できましたことに私は深く感動しております。私自身もまた、8歳の時に両親と別れ沖縄本島を後にした移民でございます。異国の地にて少しずつ富を蓄え、すぐにまた自分の家に戻るのだ、と夢と希望をトランク一杯に詰め込み、我が兄弟達に会うためにブラジルに旅立ったのです。
しかし、多くの人は、帰国の夢が叶うことはありませんでした。我々移民は全員、多大な犠牲を伴う生活に直面しなければなりませんでした。しかし、我々は決して夢を捨てず、また祖国に対する愛情と尊敬の念を決して忘れることはありませんでした。
また、重要なことは、我々がブラジルにおいて肥沃な土地そして我々を受け入れてくれる温かい社会に出会い、それらが我々に社会的地位と展望ある未来を与えてくれたことです。
笠戸丸の出航から100年という月日が流れ、我々移民及び日本人の子孫は、現在、ブラジル社会に完全に溶け込んでおり、地方及び都市部において様々な分野で活躍し、あらゆる社会から尊敬の念を持って認められています。
我々が今ある地位を獲得するまで、開拓者はその第一日目から壮絶な戦いを余儀なくされましたが、その地位は次世代の日系ブラジル人によって維持され続けました。我々は、言語、異なる習慣という壁を乗り越えねばならず、第二次世界大戦によりもたらされた衝突にも直面せねばなりませんでした。しかし、我々は決して気力を失うことはありませんでした。
また、我々は、倫理及び道徳という厳しい規律に従うことを決してやめることはなく、この美徳は、我々の行動規範の一つとしてブラジル国民に全面的に認められております。
長い年月をかけ、我々の夢と希望は、新たな生活を築き上げ、我々を兄弟姉妹の如く受け入れてくれた素晴らしい国に貢献するためのエネルギーに変わっていきました。そのお陰で、我々はその活動を十分に発展させることができたのです。今日、日本人移民がブラジル農業に果たした貢献は誰もが認める事実です。
また、日本人移民が教育を大事にしてきたことを強調しなければなりません。我々は自らを犠牲にしたとしても、子供に対する教育については決して疎かにすることはありませんでした。多くの場合、日系社会が教育を優先度の高い事項と位置付けました。遠く離れた小さな移住地にさえ、必ず一つの学校がありました。その努力の結果が現在現れているのです。日系人は、最高の学歴水準を示し、主に高等教育における日系人教師の数は傑出しています。
天皇皇后両陛下、その認識は、我々日系人だけのものではございません。その証拠に、日本人ブラジル移住百周年を記念してサンパウロ州政府教育局が実施する「ビバ・ジャパン」というプログラムがございます。
「ビバ・ジャパン」は、ブラジル人と日本人の関係のルーツについての知識を深める重要性につき学生及び教育者の関心を喚起することを目的としています。昨年開始された本プロジェクトには、7歳から15歳までの年齢層の公立学校に通う生徒約50万人がすでに参加しています。
以上のように、日本人移住百周年記念というイベントは、今や日系社会という境界を越え、ブラジル人全てが参加する国家的イベントに発展しています。これは、ブラジルが多文化共生を大きな特徴のひとつとする寛大な国家であるという疑う余地なき証明でもあるのです。
そして、このような多くの尊敬と感動の巻き起こる雰囲気の中で、徳仁皇太子殿下のご訪伯が待ち望まれております。
私はまた、この場をお借りしまして、2008年に日伯交流年を祝福できますことが我々の深い喜びでありますことをここに強調したいと思います。この記念すべき年が次なる百年に向けた新たな日伯関係の大きな一歩を示すものと信じております。
天皇皇后両陛下及び皇太子殿下並びに日本国民の皆様全ての御健康と御多幸をお祈りしますとともに、自らに許されました最高の栄誉に対する感謝と感動の念を改めて申し述べまして、私の挨拶の言葉とさせていただきます。
2008年4月28日 - 旧神戸移住センター保存・再整備着工宣言式
神戸市長 矢田立郎氏の挨拶
 本日はお忙しい中、旧神戸移住センターの保存・再整備"着工宣言"式典にご出席いただき、ありがとうございます。主催者を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。
本日はお忙しい中、旧神戸移住センターの保存・再整備"着工宣言"式典にご出席いただき、ありがとうございます。主催者を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。
今年、2008年(平成20年)はブラジル移住100周年記念の年です。神戸は、ブラジル移住とは非常に縁の深い街で、日本人のブラジル移住は、今からちょうど100年前の今日、1908年(明治41年)4月28日に、最初のブラジル移住船「笠戸丸」が神戸港から出航したのが始まりです。
また、その20年後の1928年(昭和3年)には「国立移民収容所」が設置され、それが後に「神戸移住センター」と改称し、1971年(昭和46年)に閉鎖されるまで、実に約25万人もの移住者が、神戸港からブラジルを中心とした南米に旅立っていかれました。
この「神戸移住センター」で、多くの移住者の方が、大きな希望と不安を胸にいだき、出国前の短い期間を過ごされました。移住センターとしての役割を終えてから、すでに30年以上が経過していますが、今でも多くの移住関係者の方々がここを訪ねて来られます。移住関係者にとって、ここはいわば"心の故郷"として、非常に大切な存在となっております。こうした多くの移住関係者の思いを背景に、この旧神戸移住センターの保存を求める声が、神戸市に寄せられるようになりました。
そこで、神戸市ではブラジル移住100周年記念事業として、今では国内に唯一現存する移住関連施設となった、この旧神戸移住センターの保存・再整備事業を行うことといたしました。笠戸丸の出航から100年となる本日、2008年4月28日、ここに旧神戸移住センター保存・再整備工事の"着工"を宣言いたします。
改修工事は5月末頃に始まり、約1年の工期を経て、神戸市とブラジルのリオ・デ・ジャネイロ市との姉妹都市提携40周年記念の年でもある2009年(平成21年)5月末に再オープンする予定です。新たな旧神戸移住センターでは、現在の「神戸移住資料室」を大きく発展させた「移住ミュージアム」を設置するほか、日系人を中心とした在住外国人の支援や、芸術を通じた国際交流の施設として生まれ変わります。
「旧神戸移住センター」の保存・再整備は、国内のみならず、ブラジルの日系人社会でも注目されております。神戸市としましても、多くの方々の期待に応えるべく、再オープンに向けて事業を着実に推進していく所存ですので、ご協力をお願い申し上げます。
また、再整備にかかる「基本計画」の策定など、本日ご出席の皆様の多大なご協力を賜りました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。
最後になりましたが、皆様方のご健勝とご活躍をお祈りいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
2008年4月28日 - 「友情の灯」採火式
日伯交流年兵庫県実行委員会 副委員長
上島達司の挨拶
|
|
本来ですと日伯交流年兵庫県実行委員会の西村委員長が、挨拶いたすところでございますが、皇太子殿下をお迎えするため公館に向かわれましたので、代わって副委員長であります私上島が、ご挨拶申し上げます。
|
| 採火した火を掲げる 上島副理事長 |
本日は、終日にわたって100周年行事が詰まっている中、ブラジルへ送ります「友情の灯」採火式に、早朝よりご参集いただき感謝申し上げます。
また、ブラジルから「日本移民百周年記念協会」の上原会長、松尾執行委員長ほかにもご列席いただき有難うございます。
日伯協会は、2年前にいち早く「移住100周年委員会」を立ち上げました。その後まもなく、ブラジル日本移民百周年記念協会から「友情の灯」を送って欲しいという要請を受け、我々としましても「100周年の大きな事業」と位置づけ、実現に向けて取り組んでまいりました。
「友情の灯」は、世界中を騒がしておりますオリンピックの聖火とは違いまして大変意義深いものであることをお伝えしたいと思います。
と申しますのは、初期のブラジル移住者の多くは、遠い異国で入植された時代には電気はなく、ランプの薄暗い灯りを頼りに、一生懸命働き生活を支えてこられました。いわば、「灯(ひ)」は移住者の将来への「夢」と「希望」の象徴でございます。
そこで、ブラジルへ出られた47都道府県ご出身の方々の思いがいっぱい詰まった、ここ旧神戸移住センターの屋上で「採火」を行い、ソーラーパネルで電気エネルギーに変えて蓄電した電池を、送り出すことにした次第です。
どうか、「友情の灯」が、無事にサントス港に到着し、来る6月21日サンパウロで開催される「日本移民100周年記念式典」において灯され、日本とブラジル両国間の新しい100年の絆が始まることを願いまして、簡単ですが主催者の挨拶といたします。
2008年4月28日 - ホテルオークラ神戸
原 久美 記念ボサノバ・コンサート

2008年4月28日 - 記念レセプション
日伯交流年兵庫県実行委員会・委員長 西村正の挨拶
 ブラジル移住からちょうど100年となるこの節目の日に、皇太子殿下のご臨席の下、日本とブラジルの架け橋として活躍してこられた関係者の皆さんと共に、移住者の功績を顕彰し、両国の交流をいっそう深める機会をもてることを大変光栄に思います。
ブラジル移住からちょうど100年となるこの節目の日に、皇太子殿下のご臨席の下、日本とブラジルの架け橋として活躍してこられた関係者の皆さんと共に、移住者の功績を顕彰し、両国の交流をいっそう深める機会をもてることを大変光栄に思います。
まもなく、時刻は5時55分になろうとしております。明治41年4月28日、781名を乗せた最初のブラジル移住船「笠戸丸」が神戸港を出航したまさにその時刻が近づきつつあります。本日午前、かつて移住者が出発前の日々を過ごした「旧神戸移住センター」の屋上で「友情の灯」を採火いたしました。兵庫県民をはじめ全国の人たちの友好の願いが込められたこの灯は、その5時55分にサントス港に向け送り出されます。そして当時の移住船が通った航路をたどって運ばれ、6月にサンパウロで開催される記念式典の会場で灯されることになっています。
ブラジルの皆さんは、はるばる地球の反対側から運ばれた友情のシンボルを見て、移住者が歩んできた歴史に思いを馳せるとともに、きっと将来の両国関係の展望に「希望の光」を見出してくださることと信じています。
両国の豊かな交流の礎を築いたのは、移住者とその子孫の皆さんの長年の活躍をおいてありません。移住後の決して平坦ではなかった道のりを歩み、日本と中南米をつなぐ架け橋となってこられた皆さんに、改めて深い敬意を表すとともに、この関係をより深めていくために私たちも一層の努力を重ねていくことをお誓い申し上げたいと思います。
いま神戸を旅立つ「友情の灯」のように、両国の関係が未来に向けて一段と輝きを増すことを心から願い、私の挨拶とさせていただきます。
2008年4月28日午後5時55分 - 笠戸丸出港時刻/神戸港メリケンパーク岸壁
「友情の灯」送り出し
 |
 |
|
移民船最後の「ぶらじる丸」川島船長の手で |
||

この「友情の灯」の装置は西廻りのコンテナ船で、 43日間をかけてブラジル・サントス港へ運ばれました。
2008年4月27日 - JICA兵庫(HAT神戸)
記念講演会
 講演内容
講演内容
「ブラジルの可能性と日本人への熱い期待」
講師
山根 一眞
(ノンフィクション作家、元NHKキャスター)
2008年4月9日 - 神戸ポートアイランド L-15埠頭
「神戸の水」出荷式
 |
 |
| 神戸港での送り出し式 | パラナグア港での荷揚げ式 |
一般財団法人日伯協会から「神戸の水」4万本をサンパウロ州とパラナ州の式典に寄贈。
水はハウス食品株式会社のご協力によって提供いただきました。
輸送は通関業務を山九株式会社、船舶輸送は株式会社 商船三井にそれぞれご協力頂きました。